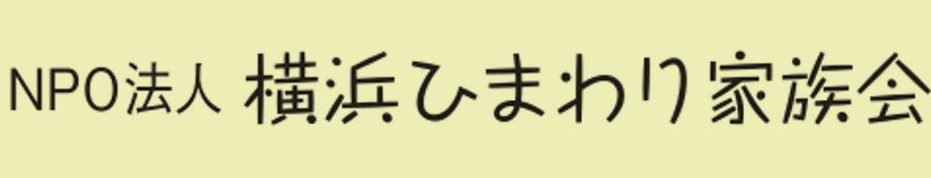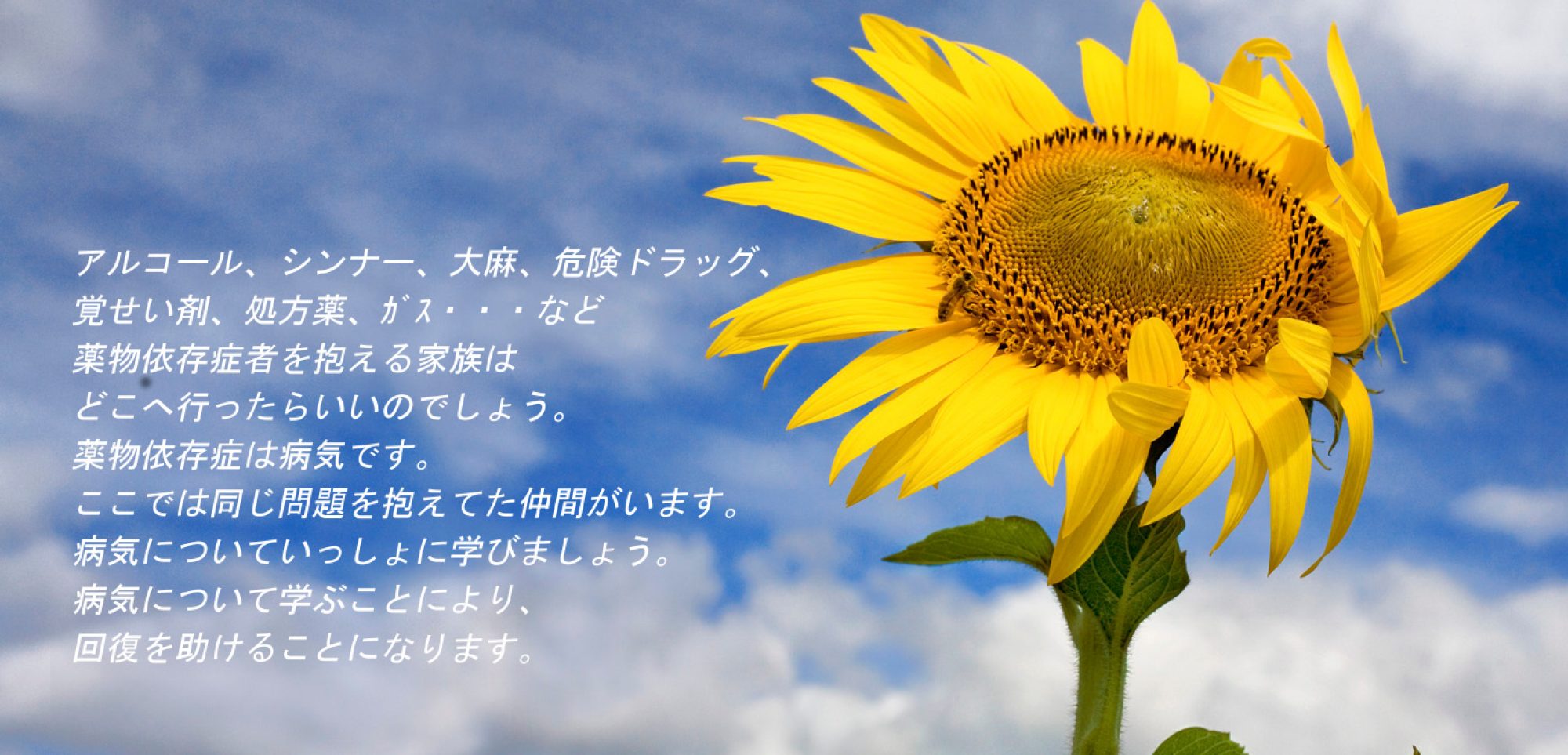講師:横浜保護観察所 統括保護観察官野沢暁生氏
今回の研修会は、横浜保護観察所で、執行猶予中の薬物事犯者の更正指導にあたっている統括保護観察官、野沢暁生氏のお話でした。
更生保護とは、犯罪や非行の予防と、その再犯防止、更生とともに、社会復帰へ導いていくことです。
又、矯正施設内処遇から社会処遇(社会の中で暮らしながら更生していくこと)に移るとき、それを円滑に移行するという、大切な役割があります。
さらには、犯罪や非行から、社会復帰までの流れの中で、保護観察、執行猶予がついたとき、出所後の受け入れ先の調整、保護司との調整も大切な仕事となります。
保護観察官には、多岐にわたる業務がありますが、各観察官の仕事内容に、偏りがないように、各業務にわかれているとのことです。
数々の犯罪の中で、薬物事案は再犯率も高く、各薬物によって対象年齢の違いもあります。覚醒剤は、成人の方が少年よりも使用率、再犯率が高く、大麻に関してはその逆で、若年層の使用率が高いです。そういった、薬物依存症の人たちに行うプログラムに関しての業務も多岐にわたり、外部の部署や施設関係者との調整、当事者に対する、処遇、そしてそれにまつわる事務作業と、保護観察官の仕事の多さに驚きました。日本では、薬物に対しての社会のスティグマが高く、理解のされにくい事案となります。まだまだ薬物依存症者を排除しようという傾向もあり、大きな課題と言えます。
また、大麻使用罪もてきたことにより、使用してしまう苦しさを相談できずに過ごしている当事者が増える中で、規制するということが先行しています。依存症者、犯罪、非行などに対する考え方を変えていくことの難しさを感じています。そして、援助的な考えを広めていくは。。。ということがも今後の課題です。
本人は刑務所内や、保護観察中に、義務的にプログラムを受けますが、家族も引受人会で勉強をさせてはどうか。。との質問が出ました。本人と同じように家族がプログラムを受けることで、依存症は病気であるというこをきちんと理解ができるのだと思います。家族が変わると本人も変わる。。というのは、どこでも聞くはなしです。
しかし実際は引受人会での家族用のプログラムはなかなか難しいのが現状だそうです。これは保護観察官の仕事が多く、なかなかそこまでは手が回らないということですが、家族に対して援助している家族会や、家族の自助グループに繋げ、家族にも回復のチャンスが訪れるよう、連携をしていくことが大切で、そこはすでに行ってくださっているとのことでした。
今回の野沢様の話の中で、多岐にわたる仕事内容のなかて、常に依存症者に寄り添い、動いてくださっている保護観察官の皆様のことが少し理解できた気がします。
ありがとうございました。
カテゴリー: 研修会
2025年6月28日(土)横浜ひまわり家族会研修会
6月の研修会は、DARC茅ケ崎代表の藤村現氏、施設長小宮勤氏でした。
まず小宮さんからのお話です。
神奈川県小田原生まれです。会社を経営されてるご両親のもとに、2人の姉の下に長男として生まれた小宮さんは、その立場から、いろいろな思いを感じてきたそうです。
社員や取引先の人たちからは、「坊ちゃん」と呼ばれ、父親より、そういった人が遊び相手でした。
家族に対してはいい顔をしてやり過ごし、心の中では、素直に受け止めることもできず、大人びた言葉で返す子供でした。
人のモノが欲しくなったら盗む、脅して奪うなどで自分の欲求を満たし、自分自身を保ってきたとのことでした。
親には言われていないのに、家を継ぐということにプレッシャーを感じ、家に居場所を見つけられず、小学生のころから家出を繰り返しました。
・・・中学、高校・・・そして、薬物・・・
中学では体も大きくなり、バイクを盗み、乗り回し、行動範囲が広がっていきました。そして、高校進学も、「どうせ、プロにはなれない・・・」と、サッカーでの推薦を蹴り、家業に役立つようにと工業高校に進学しました。
16歳で薬物に手を出し、その不良仲間をかっこいいと感じ、その中にいる自分に価値観を見出します。
そこでの付き合いやふれあいで自分を保てたとのことです。
その後使用頻度が増え、21歳で、覚せい剤を使用しました。それまで、何となく使っていた薬が、初めて、「良い物」と、認識します。これもまた使用頻度が多くなるにつれて、お金が足りなくなってきます。
友人をだまし、脅し、薬物第一になったからだと心はいろいろなものを奪っていきました。23歳で借金もしましたがそれは、父親が「尻ぬぐい」してくれたとのことです。
・・・逮捕、回復へ・・・
そんな日々が変わる時を迎えます。27歳で初めて逮捕されて、その時は「これでやめられる」と、ほっとしたそうです。
留置場の中でどうしたら辞められるかを、初めて考えることになります。
その頃家族は家族会につながっており、「家には帰ってこないでほしい」と、言われたそうです。釈放後行く当てもない小宮さんに声をかけてきたのは、昔の薬物仲間だけでし
た。そのまま再使用し、死にたい、助けてほしいと、家族に連絡をとりました。「ダルクに行くなら助ける」と言われ、小宮さんの回復が始まりました。
・・・・人との繋がりと縁・・・
家族会に繋がっていた家族は、本人への正しい対応をみにつけていました。そして、小宮さん本人は、その時々、数々のタイミングで受け取ることができました。先ゆく仲間の笑って生きる姿が12ステップとともに自分の中にも入ってきたそうです。
回復とはシンプルに「仲間と同じ事をすること」だそうです。回復者として、そしてスタッフとしてもたくさんの経験を積み、今は施設長として、伴走者として、依存症者により
そって日々忙しくしています。結婚されて子供も生まれたとの事。
最後の、病気とうまく付き合うことができる、病気を出さずに生きる、自分の弱さやパターンを、ミーティングで振り返る・・というお話は、私たち家族にも共通する話だとおもいました。
◆次に、藤村さんのお話です◆
藤村さんのお父さんもお母さんもそして兄弟も福祉関係の仕事についているそうです。勉強を強要されず、わりと自由に育てられたとのことです。ただ、きちんとした正装で撮る、家族写真が嫌だったという記憶は強く残っているそうです。
小さいころから手癖が悪くうそをつきだまし取ることを、悪いことと認識していなかったとのことです。プログラムをやるようになり、自分は薬が問題だと思っていたのが、
小さいころのことを思い出すと、その頃から問題は始まっていたとに認識したそうです。
・・・問題は家族の中に・・・
アディクションは、アルコールやたばこから始まるといわれていますが、藤村さんは小学生でたばこを吸っても、こんなもんか、と感じ、また、ビールの泡をなめたりしてい
ました。
・・・小学校、中学校・・・
1時間もじっと座ることができず、授業を抜け出す子供でした。しかしスポーツはすきで、人気者だったそうです。
4年生で転校することとなり、転校先ではじめてたばこを吸い、それでもサッカーもして過ごしました。
中学は不良ブームで徐々に非行に走りました。その先輩に誘われて、シンナーを使い始めます。まわりに弱く見られたくないといった思いからでした。その後は両親、大人の言葉は耳に入らず、悪い仲間の言葉だけを信じて、生きるようになります。
・・・17歳で覚せい剤・・・
やめたくてもやめられず、自尊心や、気分が落ち込み、その気持ちからのがれるためにまた使うという繰り返しになっていきました。
依存症は家族を巻き込む病気です。そんな中でも母親はいつも「これから、どうしたい?」と、怒らずにきいてきました。
親が家族会に行き、正しい親の対応と、距離の取り方を学んでくれました。そして、いわゆる愛のある「突き放し」を、したそうです。それが、ダルクに行ってみようか…と
考えるきっかけに、なりました。
35歳で初めてダルクで「依存症という、病気だよ」と言われたときは、救われた気持ちだったそうです。自分から、遠くに行きたいと、沖縄にわたり、そこから回復が始まり
ました。
依存症という病気は常にきもちをネガティブにもっていきます。新しい仲間は一番辛い。。。そんな気持ちを理解して、代表として過ごされています。最後に「シラフでいれば、本人も、家族も幸せ。。。」との言葉をいただきました。
今回も、お二人の話から、家族としての在り方のヒント、また私達にはなかなか理解できない、依存症者としての心の中の声をたくさん聞くことができました。私たち家
族も、少しずつ前にむかって歩いていけるように、家族会に参加していきたいとおもいます。
2025年5月24日(土)横浜ひまわり家族会 研修会
講師:群馬ダルク
施設長 福島ショーン氏、代表 平山 晶一氏、
5月の研修会は、毎年来ていただいているお二人のお話でした。私たちは楽しみにしていますが、お二人も毎年楽しみにしてくださり、また、自分の成長にもつながっているとの事で、大変うれしく思います。お二人が行ってくださるプログラムは、家族参加型です。なので私たちも聞くだけではなく、考え、発言し、仲間の話にも耳を傾けて、今からすぐに実践できることを、教えていただけます。 今回の研修会の内容は、依存症本人には、「これだけは言わないほうがいい言葉」についてです。 私たち家族は、依存症の家族に対して、なぜ?どうして?と常に思ってしまいます。そしてそれは、家族にとっても本人にとっても、とても辛いことなのだと思います。依存症本人は、再発と失敗を繰り返します。その時突き放す一辺倒ではないということも今は、言われるようになってきました。今回は、言わないほうがいいという言葉を学ぶとともに、依存症者 を理解できるようになる研修でした。家族が本人と話すときの言葉、又その時の思考を、どのようにすればお互いに傷つかず、少しでも良いほうに向かうのかを教えていただきました。
『依存症本人に言わないほうがいい言葉』
⑴ [また?」
依存症はWHOで認められている病気にも関わらず、世間には病気と認めてもらえず、本人や家族でさえもそれを認めることが難しい病気です。それは検査結果に出るわけでもなく、精神論で理解しようとするからです。ですから失敗や再発した時に、家族は「またそんなことしたの?」「また問題おこして!」と言いがちです。依存症は再発する病気です。失敗する病気なのです。家族はそこのところを理解できてくると、本人がどうというより自分が楽になり、また本人にもつらい言葉を投げかけなくなるのではないでしょうか。本人は、誰よりも、「治さなければ」「何とかしなければ」と、思っています。何か起きたとき、家族は、良いも悪いも言わず、「こういう病気なんだ」と思えるよう学んでいくことが必要です。もし何か言うとしたら・・・。「あなたの頼るところは、ここ(家族)じゃないよね。」「病院や、自助グループは?」などを選んで、話しかけましょう。時として離れてあげましょう。離れることで、本人が生きるコツを覚え、自立に近づくことができます。
⑵「がっかりした」「頭にきた」
この言葉も私たちは言ってしまいがちです。これは本人に対する期待と理想が大きいために言ってしまう言葉です。依存症本人は、生きづらさを和らげるために、使い、飲み、依存行為をします。それ以外の楽になる過ごし方を知らないのです。そして、失敗や再使用があったときは、誰よりも本人ががっかりしています。また、依存症物質や行為が止まれば、すべてがOKでしょうか?それは、違います。本人は使っていてもやめても、心も体もボロボロなのです。
⑶ 何度も繰り返し同じこと(アドバイス)を言う
家族は、良かれと思って、また、ここぞとばかりに同じことを何度も言うことがあります。しかし、それをしたところで、良い結果がうまれたでしょうか?うまくいかなかったのではないでしょうか。そんなことを言いそうなときは放っておく、その場を離れることもいいでしょう。自分のやり方、言い方を変えて、家族会で学んだやり方をしてみましょう。がみがみと長いこと同じことを言っても本人は「早くその場を去りたい」と思うだけだそうです。アドバイスしすぎると、本人が学び自分で解決する力をつけることを、妨げてしまいます。
⑷ 「意志が弱い」「根性がない」
依存症は気持ちや精神論では戦えない病気です。しかし、治療すれば、いろいろなものをとり戻せます。なぜ、やめられないのでしょうか?・離脱の苦しみ
やめるのも、やめることに立ち向かうのも辛く、肉体的にも、精神的にも辛い時期があります。それでも、仲間の中で、仲間とプログラムをやり続けることで、いろいろなスキルを学び、様々な安定を、手に入れていけます。
・重複障がい
診断されている、いないにかかわらず、重複障がいがあると、同じ失敗を繰り返すことが多いです。それにより辛さが増し再発しやすくなります。障がいを理解し、依存症の症状が落ち着いたところで、発達の治療をしましょう。・社会的、個人的スティグマ社会が依存症に持つレッテル、そして、本人の中にある自分にレッテルをはること、これにより、本人は「どうせ、自分なんか」と、言う気持ちになり、再発しやすい状態になります。
最後のQ&A
・マリファナは、軽い薬物ではない
・本人は使う理由を、使う言い訳にする
・女性の回復の仕方は、トラウマが関係していることが多く、難しい
お二人の研修を聞き、依存症という病気の深さを、あらためて痛感しました。同時に私たちにできることは、何かということも再認識できました。家族が言ってしまいがちなことを、言わない、ほかの言葉で言い換える、言わないで離れる、心は差し伸べてもすべてに手を出さずみまもる・・・。そして、家族会で正しい知識を身に着け、仲間とともに学んでいけることの、大切さを感じました。 また、来年も楽しみにしています。
2025年4月26日(土)ひまわり家族会研修会
講師/上野ダルク 理事 篠原 義裕氏・事務局長 村澤 実氏
新年度第一回目の研修会は、このお二人をお迎えしました。日本ダルク本部から、上野ダルクに変更になった経緯などをご説明いただいた後、順番にそれぞれの人生を振り返りながら、体験をお話しくださいました。
篠原さんは、お酒を扱う家業に生まれましたが、お酒に弱く、やがてこれがコンプレックスになっていき、酒やたばこを通しての「仲間意識」から、いろいろなものにはまっていきました。まずは、お酒。これは、コンプレックスの初めのものであり、又、手に入りやすく、篠原さんが、クリーンが続かなかった原因にもなりました。そして、大麻。これは、友達が、使っているところに遭遇し、自分から「僕にもくれ」と、言ったそうです。この言葉には、いろんな感情があるとおっしゃってました。友人から、「お前ははまりそうだ。」といわれたとおり、依存症になっていったそうです。
学校を何とか卒業し、親の勧める寿司や和食関係の職場を転々としたそうです。
薬は止まることがなく、薬を使えば、寝坊、仕事を覚えられない、人間関係をうまく築けない・・・など、様々な問題を生み出しました。
「人との信頼関係」からは、ほど遠い生き方だったのだと思います。その後、実家に戻ったり、入院したりもしたそうです。入院先から、NAと繋がり、普通に働いている人も来る場所なんだと、興味を持つようになります。また、その時出会った保健師さんの勧めでダルクに見学に行くこととなり、少しずつ回復の道のりに乗りました。入寮してからも、回復が進んでからも、施設から飛び出たこともあったそうです。それでもいつの日か「続けていれば、いいことがある」と思える日が来て、今は助ける立場になりました。
施設を運営すると、いろいろな問題が出てきます。でもそれを解決するためにうまくプログラムを使い、不平、不満を訴えてくる仲間のことが、本当の意味でわっかたとおっしゃっていました。家族、依存症が病気であることを伝え、家族はそれを理解し、今はいい関係に修復できてきているとのお話でした。
この話は、私たち依存症の家族には心に伝わるものがありました。
数々の失敗とともに新しい考え方や人との関係性を築き、長い年月をかけて回復の道のりに進んだ話を聞かせてくださいました。そして篠原さんのご家族の本人に対する対応や、心の底にある信じる気持ちが、いかに大切かということを聞くことができました。
村澤さんは、お子様の不登校のお話からしてくださいました。自分を責めたこともあり、また、そのことを隠したくなる、自分の親もそう思っていたのかと、心が痛んだとのことでした。中学までは、行けなかった学校も、高校からは心機一転、通学しているとのことです。これは人は変えられないが自分はかえることができ、また娘さんを信じてあげたご夫婦の気持ちが、娘さんに伝わったのかもしれないと感じました。
村澤さん自身のお話は、「他人に好かれたい、断りたくても断われない、本音を言えない」というところに数々のことが重なり依存症になっていく話を聞くことができました。村澤さんは、中学の頃からお酒は「いやなことを忘れさせてくれるもの」だったそうです。やがて、サッカーの試合前に、緊張をとり、よく眠れるようにと、飲むようになります。本人はそれを、「薬物に反応しやすい体」ととらえていたとのことでした。そして、自分が疲れて休みたいと思っても、友達に遊びに誘われると断わることができず、飲酒したそうです。その後、友達から「ブロン」や、「大麻」を教えられ、使うことで自分の不快感情がなくなることに気づきます。高校はお酒も含め薬物も、たまに使いながら卒業しました。卒業後、広告代理店に就職しましたが、兄のいる会社、周りは大学卒業の人ばかり、年上の人を相手にしなくてはならないなど、多くのプレッシャーがかかり、その苦しみを話せる人がいなかったこともあり、苦しみました。その時頭に「市販薬があった」と使いはじめます.。薬物にお金を費やし、破綻し、盗みをするといった、生活になりました。家族にバレて、その時は心療内科で診断してもらいました。内服薬と家族のかかわりの中、アルバイトをするまでになりますが、また体調が崩れ、再度薬物に頼るようになり、今度は精神科の閉鎖病棟に入ったそうです。入院中に免許の更新で外出した時、使わずに帰れたことで、やめてみようかと考えるようになり、また、家族は家族会で学んでいたことで、少しず
つ回復に向かいました。ダルクに入り、その後も飛び出したりもしましたが、家族は家に入れなかったそうです。また、施設内でも、「今日はやめておこうかな」と思える日ができてきて、人の話に耳をかたむけ、心を開き正直に話すことを続けたそうです。その後回復を続け一度は退寮し、家族のもとで、タクシーの運転手として働きますが、心臓を患ったことでやめて、今の施設での仕事につくようになったとのことでした。
このお二人の話を聞いて感じたことは
①自分(弱点を含めた)を知ることの大切さ
②自分だけで頑張らず、人に頼ることも必要
③依存症のプログラムは、毎日の生活の中で役立つ
④自分の健康な心と体を意識する
⑤家族が家族会で学ぶことはとても大切
ということでした。
人は、自分にはできる、自分でなんとかしなければ、と思いがちです。特に依存症に関しては自分、家族だけではどうにもならないのです。そして依存症に関する問題だけでなく、生きていれば、さまざまな困難が日常を襲います。病気、介護、依存症じゃないほかの家族にのしかかってくる問題・・・。それらを、自分ひとりでどうにかできる。。と、思わないこと。専門家や、他人にお任せすることが大事で、なおかつ効果があるということ。これらの考え方は依存症のことを学んだおかげです。このことを今回のお二人の話の中から、あらためて感じ取ることができました。そしてそれができたとき、私たちは自分の成長だと、素直に感じ取っていきたいと思います。明日からの「今日一日」を、安心と、希望ですごしていくために。。
2024年11月9日(土)横浜ひまわり家族会 研修会
講師:国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 薬物依存研究部 近藤 あゆみ先生
テーマは「アディクションとトラウマからの回復」
横浜ひまわり家族会でビギナーさんを中心にアドバイスをしてくださる国立精神・神経医療研究センターの近藤あゆみ先生が今回の研修会の講師をしてくださいました。
「自分の人生に目を向け、深堀り」することは、心に目を向けることになります。イヤな気持ちやしんどい気持ちになり、苦しくなることが多いです。そんなときは無理をせず、自分を思いやることが大切です。
心がしんどくなった時には、
① 呼吸に注目し整える。
② 体にギュッと力を入れて、脱力する。
体がどんな風になっているのか、どこで感じているかをよくみる。
③好きなものを30個挙げてみる。
このようにセルフケアをするとよいです。
アディクションとトラウマには深くて複雑な関係があります。あまりにつらい時には、見ないようにすることも大切ですがどこかで向き合い、断ち切る、または和らげていく必要があります。家族の世代間連鎖や自分のなかのつながりを「安心・安全」を大事にして一人ひとりができることをやり続けることが希望に繋がります。心の傷や痛みを成長しながら目をむけていくことがアディクション当事者や家族の回「トラウマ」とは心の傷になる体験で、その影響による症状があります。心的外傷後ストレス(PTSD)は自分のコントロールを離れて再体験をしたり、無意識に回避したりずっと緊張し続けたりして様々な問題を抱えます。1回の大きな出来事でなくても継続的に経験をしてきた人でもPTSDになりえます。このトラウマは時間とともに小さくなっていくことはないといいます。傷は見えないけれど大きく残っています。
依存症の家族の本人に関する否定的感情が、実は自分が体験したしんどい出来事とつながっていることがよくあるそうです。こんな場合、どう対処どのように対処すればよいのでしょう。多くの場合、否定的感情や強迫観念への反応として「拒絶」(自分との切り離し)します。無視、無感覚、誰かのせいにする、ほかのことに没頭するなどです。傷つきや痛みを乗り越えるなかで安全・承認・愛などの基本的ニーズをみたすための戦略や防衛策をとります。しかしどこかでやはり向き合う必要が出てきます。否定的感情や強迫観念への反応を肯定(自分とつながる)していく過程に入ることです。自分の思考や感覚・感情を認める。ありのままを受け入れる。自分のニーズを調べる。ニーズを満たす、はぐくむことが肯定の段階です。これまで、家族は依存症者に振り回されてきており、自分を思いやる余裕がなかった方が多いでしょう。自分を肯定する作業は、まずリラックスして困難な状況や反応を思い出します。そして自分の思考や感覚、感情を認めていきます。感情を言葉にすることも大切です。そしてさまざまな感情とともにいることを受け入れていきます。気持ちが揺れることもあるので、呼吸が静まるまで待ちます。自分の中で最悪なものは何か、最も苦しい信念はなにかなどを調べていきます。始めはつらくても、練習を重ねるといろいろな自分の気づきにつながっていきます。さらに育むこと、自分の弱い部分が受け入れられ理解され安全であると感じられる方法を見つけていきます。つらい感情に気づき、癒す。他者に手伝ってもらってもよいのです。スカッと嫌な気持ちがなくなるわけではないけれど、いろいろな経験をして生き続けていきましょう。また最後にはリラックスして今の感じをゆっくり味わいます。自分に「大丈夫」と言ってあげることが大事です。
トラウマティックな出来事をきっかけとした人間としてのこころの成長を、「心的外傷後成長(PTG)」と呼びます。「PTG」による5つの成長は、「人間関係を信頼し重視する。精神的変容、感謝、人生の価値を理解し新しい興味を持つ、自分の強さを実感し困難に対処できる。」ことです。
アディクションとトラウマは世代を超えて家族全体を苦しめます。双方からの回復の基盤は「安全安心」と自分への思いやりです。影響と反応に気づき立ち止まれるようになることが悪循環を断ち切る鍵です。苦しみが消えてなくなることはないけれど、苦しみを経験した人ならではの気づきや成長があるということです。
家族の方が自分に向き合うときには、仲間の力があると「安心で安全」なのだと実感した研修会でした。
2024年9月2日(土)横浜ひまわり家族会 研修会
講師/横浜ダルク 副理事長 弁護士 千木良 正 先生
今回は、昨年度に続き横浜ダルクの副理事長であられる千木良弁護士を講師にお招きしました。千木良先生はカトリック教会を支援していた縁で2007年からダルクと関わりが始まりました。
社会福祉士でもあり多角的な見方で、依存症の問題に取り組まれています。近年の状況としては、覚せい剤関連の逮捕者はこの10年で半分になっていますが、大麻に関しては逮捕者数が増えており、少年の逮捕者は3倍に膨れ上がっています。若年化が顕著になっています。弁護士として薬物事犯の人たちにどう支援をしていくか、あれこれ考えるけれど無力さを感じることも多いそうです。
まずは、刑事事件としての問題について話されました。
1 覚せい剤で逮捕されたら、まずは弁護士を呼ぶことですが、弁護士にもいろいろな制度があります。
① 当番弁護士制度(私選弁護人選任申出制度)
弁護士会の当番弁護士に裁判所などを通じて接見要請の依頼を受けた時には、前もって当番弁護士の希望者を募って作成しているリストに従って弁護士が派遣されます。家族や知人もライン電話をかけることができます。逮捕者に知的障害や発達障害がある場合には、障害に配慮することができる弁護士を派遣されています。
② 私選弁護人の選任
弁護士との契約により委任。
弁護士費用については各弁護士との個別契約によります。
③ 被疑者国選制度
被疑者が勾留されており勾留された被疑者の経済状況により弁護士費用を負担することが難しい場合に本人の請求等により裁判官が弁護人を選任する制度です。
④ 被告人弁護人制度
起訴された被告人の経済状況等により弁護士費用を負担することが難しい場合に本人の請求等により、裁判所等が弁護人を選任する制度です。
2 起訴前の刑事弁護
① 弁護内容…被疑者に対して弁護の方針を助言、対応をするものです。捜査が適正に行われているかをチェックすることも大切な役割です。
② 接見禁止
接見禁止を解除を求めるか決めます。
③ 刑事弁護人の留意点
被疑者の中には罪を免れたいがゆえに虚偽やごまかしの弁解を重ねるものが少なくないので弁解の信用性を十分に吟味する必要があります。
3 起訴後の刑事弁護
① 保釈申請
保釈が許可される条件
・犯行を自白していること。
・前科・前歴(とりわけ覚せい剤事件)がないこと。
・覚せい剤や注射器等の用具が押収されていること。
・入手経路があきらかとなっており他に譲渡していない事。
・身元引受人がしっかりしており、覚せい剤関係者との接触を断つことが期待できること。
・暴力団関係者・実刑が確実視される覚せい剤の常習者は保釈が許可されにくい。
・保釈金は150万円前後が多い。
② 情状弁護
・覚せい剤の入手経路と仲間をすべて明らかにすること。
・覚せい剤を使用してしまったときの心境を明らかにすること
・生活環境を改善できるか。
・親族の協力を得られるか。
・病院への入通院や薬物依存者の回復支援団体への参加。
・しょく罪寄付(被害者支援団体への寄付など)
③ 裁判が終了したあと控訴をするか否かを判断するまで。(私選弁護人は控訴審を担当することもある。)判決確定後のケアについては基本的には関わらない。
弁護士はダルクを知っている人が少ない状況です。発達障害なども理解している人は少ないようです。
4 判決
① 初犯…懲役1年6か月 執行猶予3年
② 再度の執行猶予…覚せい剤で再犯者に言い渡される刑が1年以下になることはほぼない。
③ 実刑後の再犯…7年~10年程度あいていると執行猶予付きの判決の見込みは高くなる。
薬事犯罪については、ある程度刑罰が決まっているのに、なぜ弁護士が必要なのか?国家を相手に否認事件を一人で戦うのは厳しい。法廷でたった一人の味方が弁護士だという気持ちで臨んでいるのだそうです。
5 身柄について
・執行猶予判決の場合…勾留中であっても判決当日に身柄を釈放されそのまま帰宅できる。
・実刑判決の場合…起訴時に勾留されていなかった場合は、判決が確定するまでは収監されることはない。保釈中であった場合は、実刑判決の言い渡しにより保釈は失効する。判決直後に検察庁の職員が身柄を拘束
・収監される。
・仮釈放…実刑に処せられて刑務所に勾留されている受刑者について、改悛の情がある場合に、一定の刑期を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放できるとする制度。期間満了までは保護観察に付する。
・一部執行猶予制度…刑期の一部である懲役6か月を2年間の執行猶予としその猶予期間中、被告人を保護観察に処する。犯情の軽重や犯人の境遇その他の情状を考慮して社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ相当であると認められること。
次に、民事事件としての問題については以下のことを丁寧に説明してくださいました。
1 借金の問題
① 自己破産…裁判所の手続きにより、債務の全額を面積させる手続き。
② 個人再生…一定の金額を分割で支払うことにより、残額を免除してもらう。浪費などの事情があっても利用は可能。
③ 任意整理…債務者との間で分割弁済の和解をすることで借金の整理を行う。生活保護受給者中は、任意整理をして返済することは認められていない。借金問題は、治療施設に入る前の生活の中で起こっていることが多い。借金の消滅時効などもあるので、専門家に相談することが賢明です。
そして、他害行為についての家族の責任として
1 精神障害者の責任能力が否定された場合
その場合は原則として、その者は損害賠償義務を負わない。
2 責任能力がない場合でも民事上の責任を負う場合
・例外として故意または過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りではない。
例として、違法薬物を使用して第3者に損害を与えると予見できた場合などはこれにあたる。
3 家族に責任はあるのか?
・責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負うものはその責任無能力者が第3者に加えた損害を賠償する責任を負う。
・精神障害者の家族は監督義務者なのか?…判断は事例によって異なる判断が必要であるので専門家に相談した方がよいようです。
借金暴力事件など家族の責任についても丁寧に事例を挙げながら解説してくださいました。
一筋縄ではいかないことも多いので、困ったらダルクのスタッフや弁護士などに助言を仰ぎ、落ち着いて対処するのが一番良いように感じました。
質問の場面では、それぞれの家族が抱えている保釈請求の必要性や借金などの問題を尋ね、わかりやすい回答を得ることができました。
ダルクにつなげようと弁護士が頑張っても本人にその気持ちがなければ繋がりにくい。執行猶予になることを本人も保護者も知っているとなおさら切迫感がなく、回復にはつながらないと感じているそうです。少年事件では、鑑別所で自分で考えることや社会に出ることも大切です。家庭環境によっては、鑑別所で安全に暮らすことが必要な時もあるそうです。
弁護士ももっと依存症に関する知識を持っていてほしいと切に感じているそうです。
裁判で弁護士がつくということは、国家を相手にする法廷でたった一人の味方がいるということだと話されていました。
2024年1月27日(土)横浜ひまわり家族会 研修会
今日の研修会は栃木ダルクの代表理事、栗坪千明氏を迎えて行われました。

栗坪氏は28歳のとき(1997年)に茨城ダルクに入寮し覚せい剤を止めることができました。覚せい剤は20歳ころより使用、その前はいわゆるツッパリで仲間から覚せい剤が回ってくる生活でした。建築士として働いていたころは、バブルで仕事が非常に忙しく建築士の仕事が好きで充実していたそうです。そのころは薬物を使うこともなく、仕事に没頭していました。バブルがはじけ仕事がなくなってきたころ、苦境を乗り越える力がなく覚せい剤にのめりこんでいったようです。薬物を使用中に家にあった日本刀で竹を試し切りしていた姿を見て母が警察に通報。やってきた警官が栗坪氏の腕の注射痕を触りながら、「君は薬物をやったんじゃないよな?」と尋ねてくれて「やってない」と答えたら回復への道につながったと言います。ダルクに入寮後は日本刀を振り回していたことが知れ渡っていて、包丁を使う調理はさせてもらえなかったとのことです。茨城ダルクで法人申請の担当になった後、栃木ダルクの開所に携わることになったそうです。
栃木は、ダルクなど依存症に関することを受け入れる環境にはなく、別荘地の建物を借りて開所するときも大家さんから「ダルク」の名前を使わないでほしいと言われたり、公安警察が見学に来たりしたそうです。県の薬務課は「薬物使用者がいたら逮捕はするよ。」と言ったそうです。地域に連携できる機関がないのだから自己完結型の施設にするしかないと思い、今の栃木ダルクの形にするしかなかったようです。アメリカの支援方法を学び支援方法に段階があることに気づき、今の階層型システムを構築しています。
まずは「クスリ」を止めるところ、そしてゆっくり回復する場所、社会復帰を目指す場所という段階を作り利用者に卒業という希望を持てるようにしたそうです。社会復帰をする人がいないとやる気がなくなってしまいます。
支援の3本柱として、「回復プログラム」「生活力」「社会性」を掲げ、階層式にプログラムを実施していきます。ファーストステージで動機付けをし、止めていくためにプログラムに取り組みます。セカンドステージでは問題の直面化をすること、認知行動療法などを実施し、回復の道を進みます。サードステージは社会復帰を目指していきます。慣れが出てくる時期でもありますがそれは正常の回復ととらえます。自分を過信することは危険ですが、一人で生活を回していけるようにしていきます。この段階で家族との関係を再構築することに取り組みます。プログラムが終わった人にはきちんとした形で修了証を渡し、やり遂げる自信をつけられるように取り組んでいます。
家族の支援事業は家族教室を開催し、8回で1クールとしています。できるだけ両親ともに参加することが大切です。「依存症について」や「本人への対応」「家族自身の健康」について学んでいるそうです。家族関係の再構築は家族教室に参加していることが条件となり、自分の問題に目を向けて本人との関係性を見直すことや、社会復帰後の本人と家族の関係のありようについてともに考えていくようにしているそうです。
研修会に来月80歳になるという栗坪氏のお母様も来られていました。茨城ダルクの家族会をけん引して来た方で、今は地元で「ナラノン」を開催していらっしゃいます。今回は息子である栗坪氏に「出かけよう」と言われてついてこられたそうです。ナラノンをやっているのは自分がプログラムから離れないため、泣いてナラノンにたどり着く人がいる。その人と一緒にいることがご自身の安心材料だそうです。
お話の後も、研修会に参加した家族会のメンバーの質問に丁寧に答えてくださいました。
「本人がよくなっても、親が繋がっていることが再発の抑制になる。」と話されていました。
7月22日(土)家族研修会
テーマ『保護観察所における薬物依存のある人の処遇について』
今回は法務省横浜保護観察所の統括保護観察官の太田典子氏をお招きし、一般にはなじみが薄いけれども当事者と私たち家族にとっては関係が深い「更生保護」についてのお話を伺いました。
お話の内容は次のとおりです。
1.更生保護の役割
更生保護法第1条は「更生保護とは犯罪をした者及び非行のある少年に対し、社会内において適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、又はその非行をなくし、これらの者が善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けるとともに、(中略)、犯罪予防の活動の促進を行い、もって、社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進することを目的とする。」と規定されています。
国家公務員である保護観察官と民間篤志家である保護司は協働して保護観察業務を担っています。保護観察は遵守事項の義務付けと定期的な面接等を通して、保護観察対象者の生活状況の把握を行っています。実社会のなかで指導監督と補導援護の業務が補完し合うことで効果が生まれます。
住居・家族・仕事先・学校などの生活環境は保護観察対象者の立ち直りに大きな影響を及ぼすため、保護観察官や保護司は犯罪や非行を犯した人が刑務所等に入所しているうちから釈放後の住居や仕事先の調査を行うなどして立ち直りを支える環境を整えています。これは、保護観察所における更生保護が刑事司法の最後の砦、再犯防止のかなめとして、犯罪を犯した人が地域社会に円滑に戻れるよう(更生できるよう)行政や医療などにコーディネートすることがその役割であるということを明確に表しています。
なお、保護観察になじまない精神観察については厚生労働省と緊密にタイアップして縦割り行政の弊害を避ける取り組みが現在すすんでいるとのことで期待したいと思います。
2.保護観察所における処遇の実際
保護観察官及び保護司による指導の内容は、面接による接触確保と行状の把握、遵守事項を守る働き掛け、専門的処遇プログラムの実施です。
保護観察におけるねらいは、悩みや課題を話し合うことのできる関係作りを通じて困ったことを相談して解決するという体験の蓄積、特に保護司との間で自身が他者から大切に思われる経験を通じて自尊感情を持てるようになり感情が揺れ動く場面で踏みとどまる力の体得、問題の解決方法に関する知恵の習得を通じて自身の生きづらさを和らげる必要な支援(治療や自助グループ等)につながる可能性などが挙げられます。
薬物事犯者に対してはグループワークによる「薬物再乱用プログラム」が課せられます。プログラムは執行猶予期間によって相違しますが、コアプログラムとステップアッププログラムで構成されます。
プログラムの後には簡易薬物検査があるため当事者にとっては薬物を使用しないよう心理規制を受ける一方、一定期間使用することなく頑張ったことを確認する手段としての機能を有しています。よって、陽性の場合は当然、法による処分の対象になります。
プログラムにはダルクなどの自助グループのスタッフや医療からは精神保健福祉士なども参加します。特に、ダルクスタッフの同席は薬物依存の経験者かつ回復者として当事者にとっては大きな励みであり目標となり得るため欠かせない存在です。
当事者にはこのような保護観察のねらいを理解し、プログラムに真摯に取り組むことによって一日も早い更生を願いたいものです。
3. これからの更生保護 ~家族の皆様と共に~
当事者はその犯した罪により処罰を受けて刑務所に収監されたり、執行猶予で保護観察所の指導監督や補導援護を受けます。薬物依存から脱するための体制作りとして地域の専門機関による必要な治療や福祉などの継続的な提供を受けたり、当事者同士の支え合いの機会や薬物依存からの回復に配慮した住居の確保をはかってもらったり、家族の理解と協力の獲得に尽力してもらったりと、諸々のセーフティーネットが用意されます。では、家族はその間どうしたら良いのでしょうか。
実はこのことこそが家族にとって大問題なのです。
「息子がもうすぐ出所するがどうしたら良いでしょうか」
「もうすぐ執行猶予期間が満了になるけれどどうしたら良いでしょう」
こういった不安を抱えて家族会の相談に駆け込む家族が実に多くいるのです。
保護観察所はこのような家族に対しても相談支援を行っています。その内容は引受人会の実施を通じて家族の理解を促進したり、家族からの個別相談にも対応し、保護観察官及び保護司による支援を行ったり、関係機関や家族会へ協力するなどです。
家族はその時が来る前に『大切な人のために家族ができること』をする必要があることを忘れてはならないのです。家族の相談は回復のチャンスを作ります。相談する社会資源は少なくないのです。行政・医療・家族会などの自助グループで依存症を識るセミナーに参加してCRAFTなどの知識を習得し、自身を問題志向から解決志向に切り替えることによって、まずは家族が元気を取り戻すことがとても重要なのです。
私たち家族は当事者の犯罪によって私たち自身も傷付き心折れる経験をしました。しかし、当事者が更生回復の道を辿るのと時を同じくして私たち家族も回復しなければなりません。
保護観察所で日々犯罪を犯した人と接しておられる太田統括保護監察官様はじめ多くの職員の方々及び保護司の皆様の業務に敬意を払うと共に『これからの更生保護~家族の皆様と共に~』というメッセージを感謝の心で受け取りたいと思いました。
6月24日(土)横浜ひまわり家族会 家族研修会
講師:神奈川県立精神医療センター 精神保健福祉士・公認心理士の小林千香子氏
テーマ「家族の対応」
今回は神奈川県立精神医療センターの精神保健福祉士・公認心理士の小林千香子氏を講師にお招きしました。今回の講演テーマは「家族の対応」です。ひまわり家族会ではおなじみの井上恭子先生もいらしてくださいました。神奈川県立精神医療センターは依存症の専門治療機関です。小林さんは平成27年4月から勤務しており、救急と思春期外来の担当でいらっしゃいます。現在は依存症専門治療も「依存症外来」「思春期ゲーム行動症外来(中高生対象)」「レインボー外来(性的マイノリティ―のある依存症の方対象)」に分かれています。 「依存症外来」は、成人が対象でアルコール・クスリ・ギャンブル・盗み・買い物・性などの診療を行います。「思春期ゲーム行動症外来」は、家族全体の機能に目を向けて親子で共に参加できる専門プログラムがあります。家庭や学校で居場所が見つけられず、ゲームの世界だけが居場所と感じている患者が多くみられます。「レインボー外来」は性的マイノリティで他の病院では受け入れることが難しい場合が多く依存症と性的マイノリティの二重の差別や苦しみがあります。 初診患者に目を向けると、以前はいわゆる「やんちゃな男性」が違法薬物にはまり逮捕されてしまうことが多かったのですが、最近はSNSなどで知りライトな感覚で薬物使用をする「普通の人」が増えてきています。また女性の患者も増えてきています。女性の方が、習慣化が早く併存する精神疾患が多いことも特徴として見えてきます。市販薬など人を介さずに購入できる薬物使用者も多く、より孤独な状況で苦しんでいる状況が浮かびます。 依存症者の家族にはいろいろな困り感があります。本人への否定的感情が渦巻き、怒りや悲しみが大きく依存症に対して否定的な気持ちになります。そして社会の偏見と誤解がさらに苦しめます。依存症という病への理解は、少しずつ進んではいますが、まだまだ「わがまま」や「意志の問題」などと考える人の方が圧倒的に多いのが現実です。「親の育て方」「家族の責任」など非難の的になります。社会からの家族への役割の期待も家族を追い込んでいきます。そして苦しいまま誰にも助けを求められず。孤立していくのです。閉鎖的で不健康な家族に陥っていきます。「依存症の問題さえ何とかなれば・・」 家族は薬物から本人を遠ざけようとしてコントロールしようとしてしまいます。しかし家族自身がコントロールを失って巻き込まれていきます。そして被害者意識「あの子のせいですべてが台無しに」など本人への否定的な感情に支配されていきます。家族は自分たちで何とかしなくてはいけないと過剰な責任感を持って対処しようとします。自己を失って混乱していくのです。 家族の対応を振り返っていくことが大切になります。一人ではわからないことも家族会で仲間ができることによって気づきが生まれます。 「家族のしすぎ」について、わかりやすくまとめて提示してくださいました。 ・一言が多すぎる。 ・先に言いすぎる。 ・正論を言いすぎる ・答えを出しすぎる。 ・欠点が見えすぎる。 ・先回りして考えすぎる。 ・起きていない事を恐れすぎる。 ・事実をきちんと見せてなさすぎる。 みなさんは思い当たることがありますか?ほとんどの家族には耳の痛い内容ではないでしょうか。 依存症の問題はなかなか答えがでません。小さな変化に目を向けいいところを見つけていけると少し楽になります。 家族が健康でいるためには、「依存症を正しく理解すること」「適切な対応を学ぶ」「家族自身が健康を取り戻す」ことです。家族の健康のためには、依存症以外の関心ごとを増やし、かつての楽しみを取り戻す、そして複数の楽しみを増やしていくことです。 渦中にいるとそんな気持ちにはなかなかなれませんが、家族会のメンバーで支えあいながら乗り越えていける日が来ると思います。 講義後は質問にも真摯にお答えいただきました。井上先生も適宜、回答してくださり家族の迷いの糸口を見つける一歩につながるとよいと思います。若い依存症者はパワーがあり家族も振り回されます。どこかで回復につながるタイミングがあるので家族は情報を得ておくと動きやすくなります。日々のやり取りで不安があるなどの場合も、家族会で不安や迷いを口に出すことで糸口が見つかるかもしれません。
5月27日(土) 横浜ひまわり家族会 家族研修会< 家族の回復② >
講師:特定非営利活動法人 群馬ダルク 施設長 福島 ショーン氏
今回も群馬ダルクから福島ショーン氏をお招きしての研修会でした。「関係を取り戻すコツ」と題してのお話でした。
ショーン氏のお母さんは、未だに自分のことを子供扱いするのだそうです。今はショーン氏自身のベースがしっかり安定しているから崩れないけれど、会うと怖いと思うこともあるようです。
薬物にどっぷりはまっている時期でもクスリの効果が切れてくると「自分は何をやっているんだろう。」と考えていたそうです。薬物をやっていると、止めたい気持ちと、止められない気持ちを抱えて「ジレンマに陥ります。そのうえ家族からも攻撃されることが多く、つらい気持ちに拍車がかかります。
そういったときの家族の関係をこじらせないためのコツを紹介してくださいました。
本人にやってはいけないこと
① 上から見る。
これは説教などが当たります。子供扱いしている状況です。
「まだそんなことしてるのか。」「あんた馬鹿じゃないの?」「そんな子、産んだ覚えはない。」などと、言った心当たりのある家族は多いのではないですか?自立を望んでいるはずなのに、子供扱いをしてしまう。そして裁いたり、批判したりする。決めつける。説教、比較などがこれにあたります。
大人として接する、その方が本人は頑張れます。
② この問題はいつか去ると思う。
自分たちが今を我慢すれば終わると思っていませんか?大人になれば治ると思っていませんか?これは進行性の病気です。クスリを使っていなくても進行しています。
③ 強制的にやめさせようとする。
「好きに使って。」と言われた方がまだいいと感じるそうです。親の回復が強いと本人は親を責めにくくなります。親は本人にコントロールされにくい状態になります。逆に弱っていると責められやすくなります。本人の行動を強制しないことが大切です。
④ イネイブリング。
尻ぬぐいをしない。(後始末、解決)を親がしないことです。生活習慣で依存症になっていく場合もあります。本来子どもがとるべき責任を奪ってしまいます。それは大人として生きるスキルを奪うことになります。
⑤ あきらめる。
家族会に来なくなる人も多いですが、唯一の話せる場、気づきの場を失うことになります。子供のことを根性のない子、弱い子と思いがちですが、どん底を何度も経験しても、生きようとしていることを忘れないでほしい。意志は強い、生きる力を持とうとしています。どこで何が変わるかわかりません。「うちの子だけは違う。」と考えないでください。病気の力が強すぎてクスリには負けてしまいますが、少しずつ手放せればいいと考えましょう。戻らないことが大事です。失敗したら、また話してもう一度始めればいいことです。
怖さはあります。それは死や世間などです。
そして、やってほしいこと
① 常に本人の病気のことや自分の共依存のことを勉強し続ける。
家族の病気と言われる依存症。問題のあるメンバーを中心にして合わせて生活をしてしまいます。本人だけが回復しても家族が勉強しないと元に戻ってしまいます。共にいない方がいい場合もあります。自分たちの問題を学ぶことが重要です。再発する病と認識していきましょう。
② おかしいと思ったらおかしいと言うようにする。
問題と感じたらやれることをやる。後で問題にならなかったらそれでよい。自分の勘を信じることです。
③ 手放そう。
距離を置くことは大切です。期待と理想を手放すことが、お互いが楽になれる大きな要因です。親は子に対して期待と理想を大きく持ちがちです。そしてがっかりする。がっかりされた子供はつらいです。コントロールできないものは手放すこと。口論や説教をしても何も変わらないです。
その気持ちを家族会で誰かに伝えましょう。問題は解決しないけれど話すことは手放すことになります。
④ 境界線を引こう。
自分が違和感を感じていながら許すのは、境界線がうまく引けていないということです。薄かったり、なかったり。暴言やお金をせびられても許してしまう。これだけはダメだというものがなく、相手が中心になっています。自分の芯を作りましょう。超えられてもまた線を引きましょう。
⑤ セルフケアを練習してください。
長年、依存症者に集中しているから自分のことを忘れています。意識して自分のケアをするようにしましょう。これまでダメージも大きかったはずなので、自分のために「何があっても○○をする。」と決めて無理にでもやってください。だんだん楽になっていくはずです。
⑥ 褒める。
本人も周りの家族も気にかけることが大切です。
兄弟姉妹のことが質問に上がりました。兄弟もダメージが大きいはずです。本来の家族内の役割を超えて抱えていることも多く、心が傷んでいます。依存症者に目が向いてばかりで愛情を向けられないことも多いです。うつ病になったり依存症になったりするケースもあります。まずは親が回復し元気になって本来の役割を果たせることが大切ではないでしょうか。
距離感を保つのは難しい場合もあります。心の準備も必要ですが慌てないで、できることを少しづつ行い、距離を保っていけると良いですね。
最後にショーン氏は、「希望は持っていてほしい。」とおっしゃっていました。