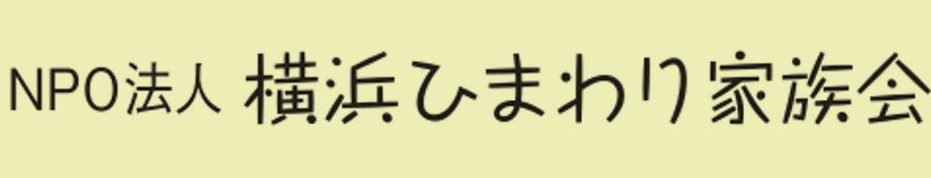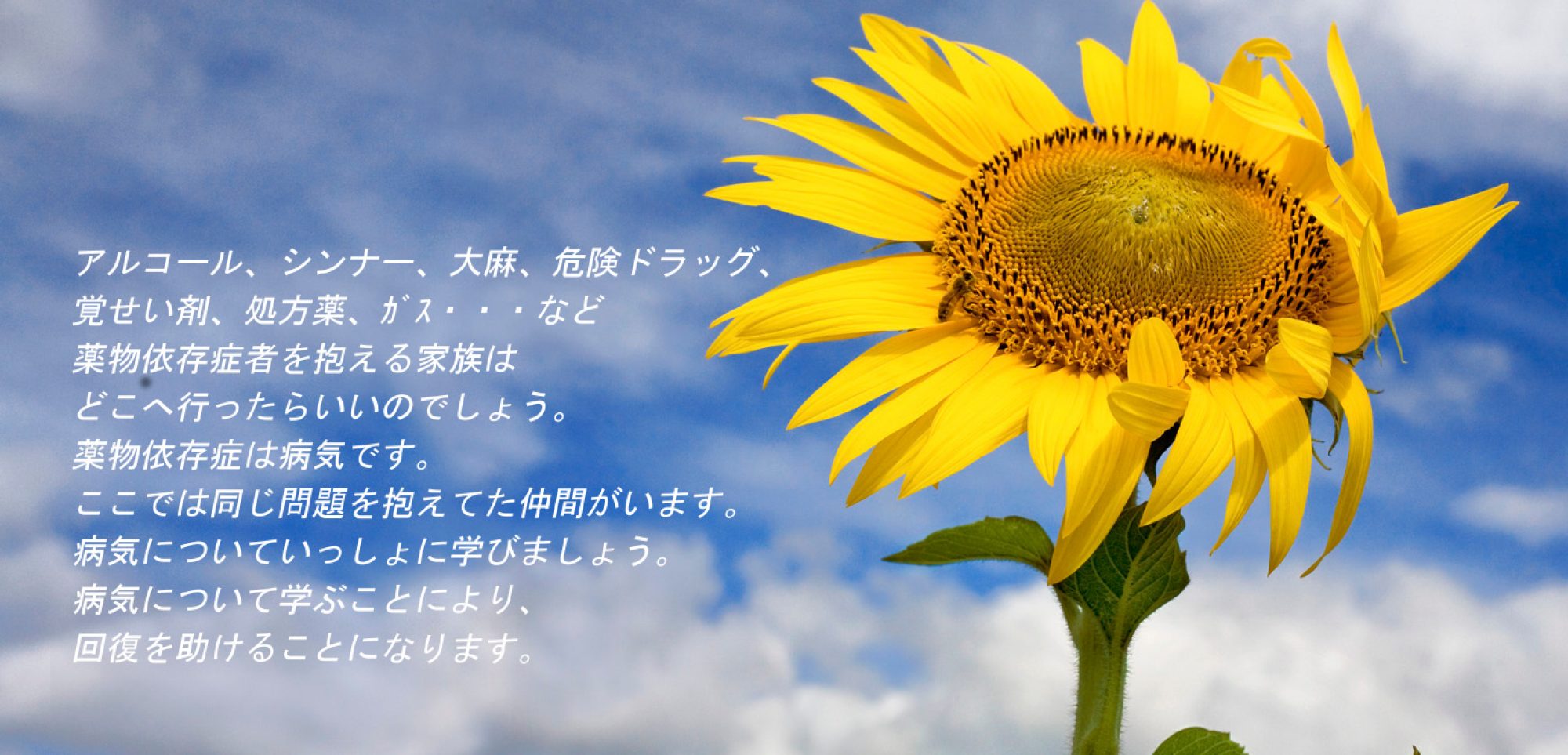2016年に始めたオープンセミナーも今回10回を迎えることができました。多くの皆さまと依存症問題の共有ができ、多くを学びができましたことに感謝申し上げます。
今回の基調講演は、神奈川県立精神医療センター依存症診療科部長の青山久美先生による『家族から始まる回復の連鎖』と題してのご講演です。青山先生のもう一つの専門である児童精神科と合わせて、小児期の逆境体験と依存症の関連についてもうかがうことができました。会場とZOOMオンライン合わせて、174名の参加をいただき、多くの方と沢山の事を共有できました。
まずは、横浜ひまわり家族会のさくらさんの体験談です。
14年間の月日、今日のことしか考えることができなかった。という冒頭の言葉に、皆うなずいていました。薬物使用に対して、親は、私がなんとかしなくては、やめさせなくてはと躍起になります。感情にまかせて泣いたり怒ったりしていたとのことです。病院に貼ってあったポスターのキヤッチコピー『依存症は愛情だけでは治らない』を見て家族会につながり、家族会の中で学び、学んだことを実践していくと、息子は少しずつ変わってきたとのことでした。依存症本人との同居生活は不安と疲労感が続く…だから、これからも仲間とともに学び続けたい。という力強い言葉をきくことができました。
次の当事者の体験談は、横浜ダルクの純さんでした。
9年前、夫の薬物の問題で家族として私達ひまわりの仲間だった純さんは、その後当事者であることをカミングアウトし、自助グループに行くようになりました。今は横浜ダルクにも、通所しています。小さい頃に家族と別れ、親がいない純さんは、預けられた親せきからも、虐待をうけることになったそうです。たばこ、シンナーを覚え、暴走族に入り、やがて覚せい剤を覚えていきました。その後出会った夫にも、覚せい剤を教えてしまい、旦那さんはどんどんはまっていきました。自分は自然とやめることができ、その中で気づいた、自分の夫に対する「共依存」。沢山もがき苦しんだ純さんは、今は自助グループの中で仲間と共に、逃げずにプログラムを継続しています。
彼女の幼少期のつらい体験は、彼女の人生を変えてしまったのかもしれません。しかし、このような体験をのり超えて、回復していく姿に希望を教えてもらいました。
基調講演の青山久美先生はひまわり家族会でも以前に講演いただきました。

今回の講演テーマは『家族から始まる回復の連鎖』です。
「依存症の人は、自分の感情にうまく気づいたり、言葉にしたり、人にSOSを出すことができず、依存性のある物質や行動で対処をするようになる。
家族は人に相談できず、自分で何とかしようとして、健康的な対処ができなくなり、家族自身の体調を崩すようになる。
ではその解決方法はどうすればよいのか。その大きな課題を、先生が具体的な事例も含めわかりやすく教えてくださいました。
➀今どきの依存症事情
②背景にある、複雑な生きづらさ
・愛着障害としてのアディクション
・依存症リスクと17項目の小児期(15歳以下)逆境体験
・信頼障害仮説
小児期の愛着障害や逆境体験が要因で、依存症になる方がいます。困難な養育環境は、心の病のリスクを高めるからです。そのような体験が、人を信じられなくなり、ストレスへの対処能力が低く、物資や行為に依存するようになります。人に頼ることができるようにになり、依存物質や、依存行為から距離をとることで、依存症からの回復につながっていくのです。とのお話しでした。
①、②についての説明の後、家族が元気になるためのお話をしてくださいました。
➂見守る家族が元気になるために。
・本人とのかかわり方を学ぶ。
・本人に話しかけるときは、「私は」を主語にして話す。
・感情にまかせない。正したい反射を出さない。
・依存症の人は、欲求や渇望があるのは当たり前の事なので、それを叱ったりしない。
・金銭的や後始末、本人の代わりに本人にとって都合のいい噓をかわりにつくなどの「尻拭い」はしない。
家族が子供の場合
子供のための支援を充実させることが必要。
子供が安心と安全を感じられ、気持ちを受け止めてもらえる場所を作る
子供たちの支援者も、依存症を知り親子で支援してもらう。
また、年齢にもよりますが、子供に「依存症」という病気について説明することも大切。
家族が大人の場合
まず、自分が元気になる。
自分に目を向け、自分がホッとできる時間、楽しいと思える時間を持てるようにする。
家族会や家族教室に顔を出してみる。
私たち家族は依存症の問題が起き、疲弊していきます。そして自己憐憫に陥り毎日が苦しくなります。しかし依存症について正しい知識を身につけ、安心して話せる仲間を見つけていくうちに、私たちは元気になれるのです。
家族が回復すると、その姿を見て、依存症者本人の回復が始まっていきます。家族会という安心安全な場所、仲間の中で回復の連鎖が始まっていくのです。
そのために家族は、愛情をもって手を放していき、本人との適切な距離をもち、家族自身が心にフタをしない生き方を学んでいくことです。どうしたらよいかを学ぶことのできる家族会の重要性をあらためて感じました。
Q&Aセッションでは、登壇者に青山先生、横浜ダルク施設長山田貴志氏、湘南ダルク代表栗栖次郎氏、横浜ダルクスタッフ ソウさん、純さん、そして、ファシリテーターに、国立精神・神経医療研究センターの片山宗紀氏でした。会場・zoom参加者から、たくさんの質問が寄せられました。

まず、本人との距離の取り方についての質問。
本人の体験や年齢、もともとの家族関係にもよりますが、自分たち(家族)だけで判断せず、それでよいのか、よかったか、など、相談、評価できる支援者や仲間がいるとよい、そして、言い方に気を付けたり家族が巻き込まれない状況を作っていくことが大事である。とのことでした。
また、もし自分に近い人が、薬物を使っていたらどうしたらよいのかの質問。
これも一人で抱えず、信頼できる人に相談して行くこと。あなたはどうしたいのかと、問いかけてあげること、など、それぞれの立場でお答えいただきました。
また「愛情のかけ方」についての質問では、
登壇者のみならず、会場からもそれぞれの立場で感想がありました。なんでもやってあげることが愛情ではないこと。家族が助けないことが必要な時もあること。障がいのあるご家族は愛情があるからこそ、自立を目指した経緯などが話された。親が子に対して、適切な距離をもって愛情を注ぐのがどれだけ難しいものか。でもそれをしなければ…。ということを痛感しました。感じるものが多い意見交換でした。
今回もたくさんの方が参加してくださいました。ありがとうございました。この依存症の問題は依存症者本人も家族も一人では抱えきれない問題です。仲間の中で元気を取り戻し回復の連鎖が起きますよう願っています。